社会人が陥りがちな読書の落とし穴と私の失敗体験
社会人になってから読書習慣を身につけようとする多くの方が、実は同じような落とし穴にはまっています。私自身も20代の頃、「とにかく本を読まなければ」という焦りから、数々の失敗を重ねてきました。
量を追い求めた結果、何も残らなかった20代前半
新卒で商社に入社した当時、私は「成功するビジネスマンは月に何十冊も本を読んでいる」という情報に影響され、とにかく読書量を増やすことに必死でした。通勤電車では速読術の本を片手に、1日1冊を目標に設定。しかし、3ヶ月後に振り返ってみると、読んだ本の内容をほとんど思い出せない状況でした。
特に印象深い失敗例が、マーケティング関連の専門書を1週間で5冊読破した時のことです。読み終えた達成感はありましたが、実際の営業活動で活用しようとした際、具体的な手法や理論を全く説明できませんでした。上司から「最近勉強してるって聞いたけど、具体的に何を学んだの?」と質問された時の恥ずかしさは今でも覚えています。
社会人特有の読書環境が生む3つの問題
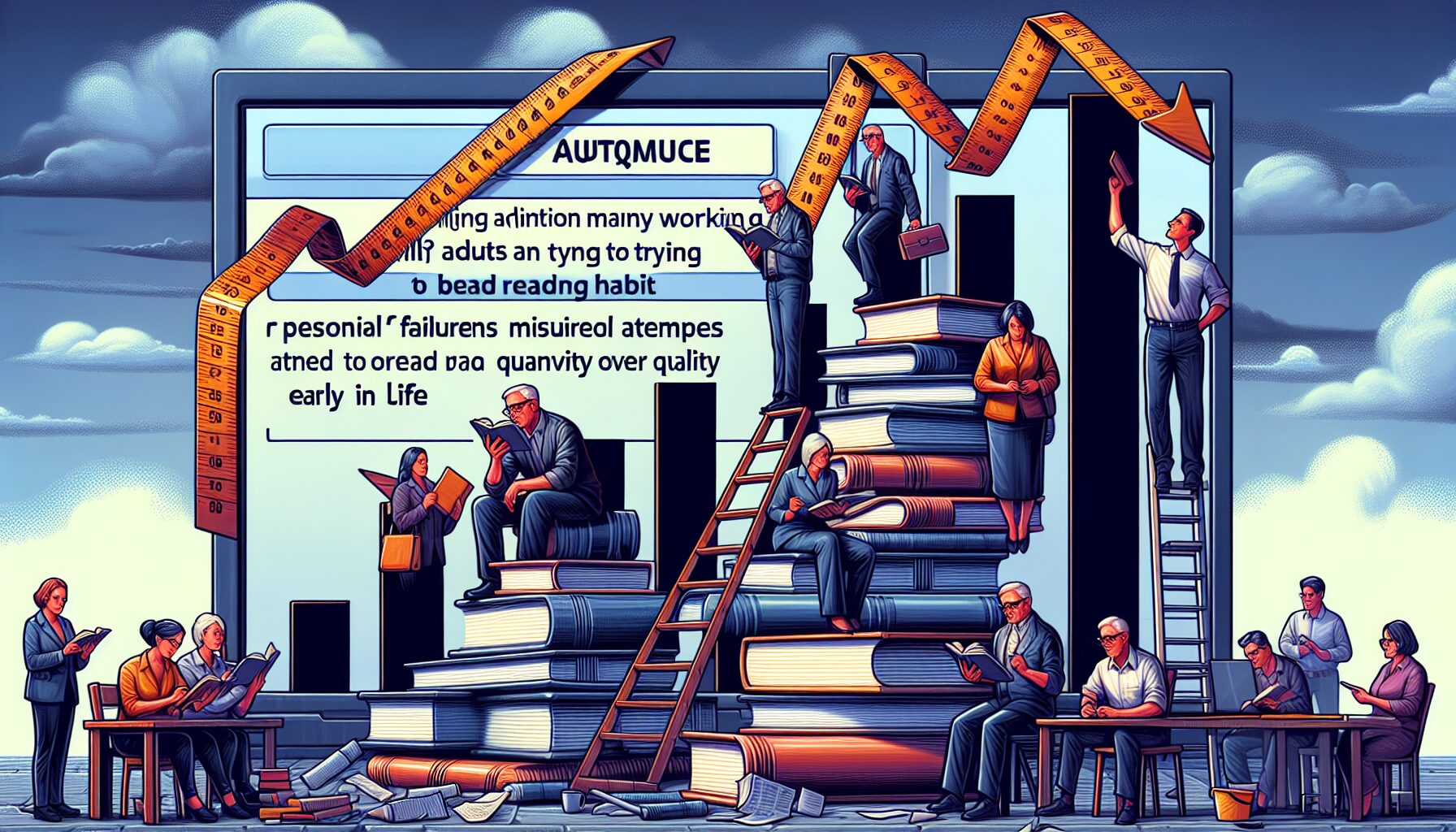
多くの社会人が直面する読書の課題を、私の経験から整理すると以下の3つに集約されます:
1. 時間の細切れ化による集中力不足
通勤時間や昼休みなど、限られた時間での読書は内容の理解度を大幅に下げます。私の場合、電車での読書時間は平均15分程度でしたが、この短時間では複雑な概念を理解することは困難でした。
2. アウトプット機会の不足
学生時代と異なり、読んだ内容について議論したり、レポートを書いたりする機会がほとんどありません。インプットのみに偏った読書術では、知識の定着率が著しく低下します。
3. 実務との関連付けができない抽象的理解
理論的な知識は頭に入っても、それを実際の業務でどう活用するかが分からない状態が続きました。特にビジネス書に多い「成功法則」系の内容は、具体的な実践方法が不明確なものが多く、読後の行動変容につながりませんでした。
これらの問題を解決するために、私は30歳の転職を機に読書術を根本から見直すことになります。次のセクションでは、その転機となった出来事と、新しく構築した読書法の基本的な考え方について詳しくお話しします。
月20冊を3年継続できた読書習慣の作り方
正直に言うと、月20冊という数字だけ聞くと「そんなの無理」と思われるかもしれません。実際、私自身も最初の頃は月3冊読むのがやっとでした。しかし、読書を「習慣」として定着させるための仕組みを作り上げることで、無理なく継続できるようになったのです。
時間の確保より「読書タイミング」の固定化

多くの人が「読書時間が取れない」と悩みますが、私が重視したのは時間の長さではなく読書タイミングの固定化でした。具体的には以下の3つのタイミングを「読書専用時間」として設定しました:
- 通勤時間:往復1時間で約50ページ進む
- 昼休み後半15分:食事後の集中しやすい時間を活用
- 就寝前30分:スマホを見る代わりに読書
この3つのタイミングだけで、1日平均80〜100ページは確実に読み進められます。200ページの本なら2日で完読できる計算です。
「完璧主義」を捨てた読書術の転換
以前の私は「1冊を完璧に理解しなければ」という完璧主義に陥っていました。しかし、社会人の読書術として重要なのは「必要な情報を効率的に抽出する」ことだと気づいたのです。
現在実践している読書の流れは以下の通りです:
| ステップ | 所要時間 | 実施内容 |
|---|---|---|
| 事前調査 | 5分 | 目次と帯文から読書目的を明確化 |
| 速読フェーズ | 1時間 | 全体を流し読みして重要箇所を特定 |
| 精読フェーズ | 1.5時間 | マークした箇所を重点的に読み込み |
| アウトプット | 30分 | 学んだ内容を3つのポイントでまとめ |
継続の秘訣は「読書ログ」の記録
3年間継続できた最大の要因は、読書ログをつけ続けたことです。単純にタイトルと読了日を記録するだけでなく、「この本から得た気づき」「仕事で活用できそうなポイント」を3行で記録しています。
このログを見返すと、自分の成長が可視化され、読書へのモチベーションが自然と維持されます。特に転職活動の際には、このログが面接での具体的なエピソードとして大いに役立ちました。月20冊の読書習慣が身につくと、情報収集力と思考の幅が格段に向上し、仕事での提案力や問題解決能力も大幅にアップします。
速読に頼らない理解重視の読書術

多くの社会人が「速読術をマスターすれば効率的に読書できる」と考えがちですが、私の3年間の実践経験から言えるのは、理解度を犠牲にした速読は逆効果だということです。月20冊を継続的に読み続けられているのは、速度よりも「確実に内容を理解し、記憶に定着させる読書術」を確立したからです。
「3段階理解法」で内容を確実に定着させる
私が実践している読書術の核心は「3段階理解法」です。これは速読の対極にある手法で、1冊の本を3つの段階に分けて読み進める方法です。
第1段階:全体把握読み(15分)
目次と各章の冒頭3行、まとめ部分のみを読み、本の全体構造を把握します。この段階で「この本から何を学びたいか」を明確にします。
第2段階:重点理解読み(60-90分)
第1段階で特定した重要章節を、理解度100%を目指してじっくり読みます。分からない箇所があれば立ち止まり、必要に応じてスマートフォンで調べることも厭いません。
第3段階:実践連結読み(30分)
学んだ内容を自分の仕事や生活にどう活かせるかを考えながら、関連箇所を再読します。
理解度重視がもたらした具体的な成果
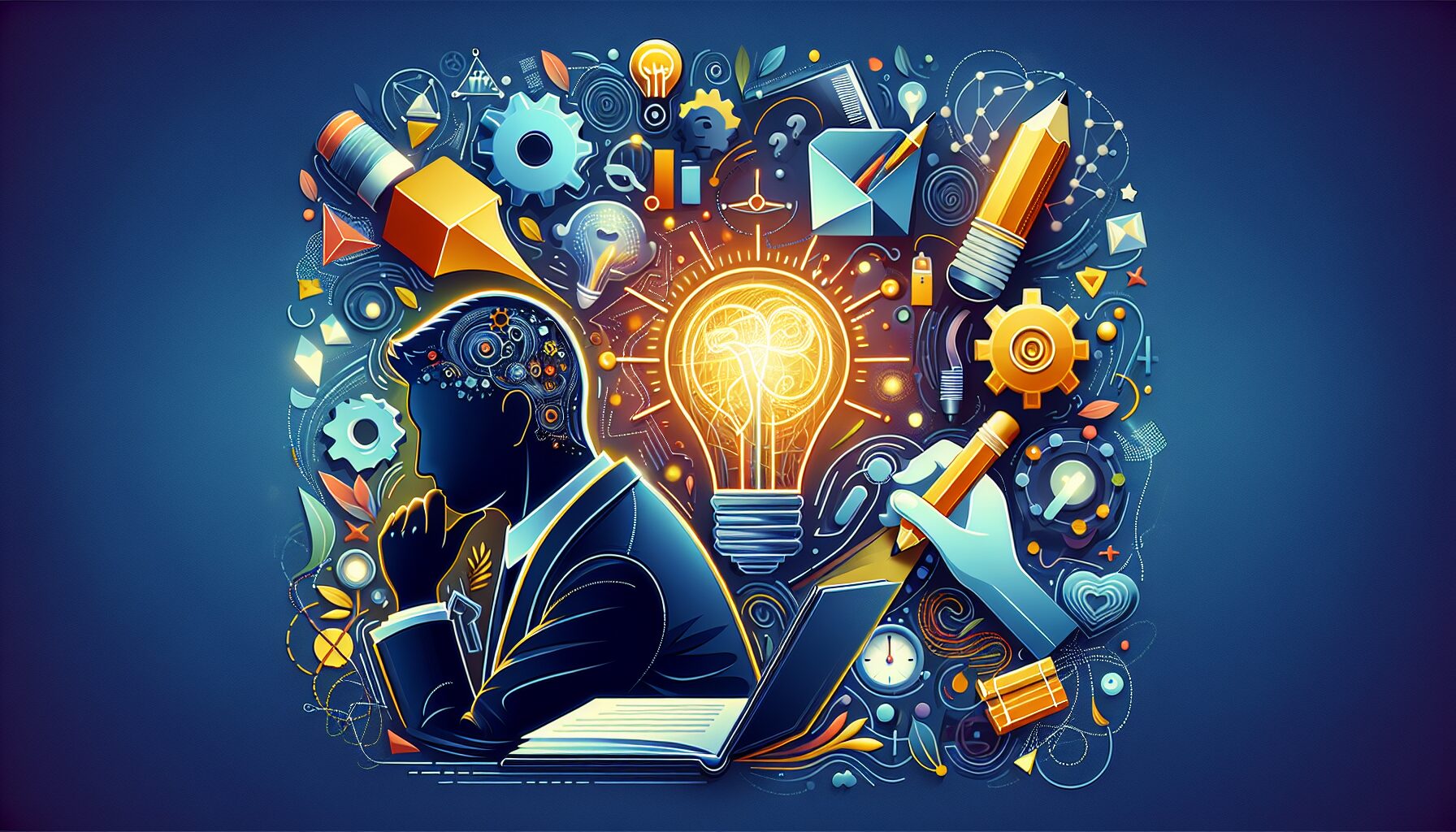
この読書術を導入してから、読書の質が劇的に向上しました。速読時代は1冊30分で読めても、1週間後にはほとんど内容を覚えていませんでした。しかし現在の手法では、3ヶ月前に読んだ本の内容でも、仕事の場面で自然に思い出して活用できています。
実際に、マーケティング戦略の企画書作成時に、半年前に読んだ『顧客心理学』の内容を応用してプレゼンテーションを成功させた経験があります。これは速読では決して得られなかった成果です。
| 読書方法 | 1冊あたり時間 | 1ヶ月後の記憶率 | 実務活用度 |
|---|---|---|---|
| 速読術(以前) | 30分 | 約15% | ほぼ0% |
| 3段階理解法(現在) | 2-2.5時間 | 約70% | 約40% |
忙しい社会人にとって「時間をかける読書術」は一見非効率に思えるかもしれません。しかし、真の効率性は理解度と実用性にあるというのが私の結論です。
記憶定着率を高める読書中のメモ・マーキング法
私が実践する3段階メモ・マーキングシステム
読書術において最も重要なのは、読みながら脳に記憶を定着させる仕組みを作ることです。私は3年間の実践を通じて、3段階のメモ・マーキングシステムを確立しました。
まず第1段階:リアルタイム反応マーキングでは、読みながら感じた感情や疑問を瞬時に記録します。重要だと思った箇所には赤線、疑問に感じた部分には青線、自分の経験と関連する内容には緑線を引きます。この色分けシステムにより、後から見返した時に自分の思考パターンが一目で分かります。
第2段階:章末まとめメモでは、各章を読み終えた直後に、余白やメモ帳に「この章の核心は何か」を1文で要約します。例えば、マーケティング関連書籍を読んだ際、「顧客の潜在ニーズを発見するには行動観察が数値分析より重要」といった具合です。この即座の要約作業により、理解度が格段に向上しました。
記憶定着率を劇的に向上させる「関連付けメモ」

第3段階:関連付けメモが、私の読書術の核心部分です。読書中に得た知識を既存の知識や実体験と結び付けるメモを作成します。
具体的には、本の見返し部分に以下の3項目を記録します:
| 項目 | 記録内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 仕事関連付け | 現在の業務でどう活用できるか | 実践的な学習効果 |
| 過去経験との照合 | 似たような体験や失敗例 | 深い理解と納得感 |
| アクション項目 | 明日から実践したい具体的行動 | 行動変容への橋渡し |
この関連付けメモを始めてから、読書内容の記憶定着率が体感で約70%向上しました。以前は読了後1週間で内容の大半を忘れていましたが、現在は3ヶ月後でも主要なポイントを8割程度記憶しています。
デジタルツールとの併用も効果的です。スマートフォンのメモアプリに音声入力で気づきを記録し、後で手書きメモと統合しています。この二重記録システムにより、移動中の読書でも確実に記憶に残る読書術を実現できています。
ピックアップ記事

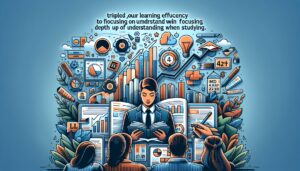









コメント