私が15年間で失敗を重ねながら辿り着いた効率的ノート術の全貌
正直に告白しますが、私のノート術の歴史は失敗の連続でした。新卒で商社に入社した22歳の頃から現在35歳まで、13年間で試したノート術の数は軽く20種類を超えます。美しい手書きノートに憧れて高級な万年筆を購入したものの、字が汚くて自分でも読めない。デジタルツールに飛びついては機能の多さに圧倒され、結局使いこなせずに放置。そんな試行錯誤の末、ようやく辿り着いたのが現在実践している「3段階ノート法」です。
失敗から学んだノート術の本質
これまでの失敗を振り返ると、共通する問題点が見えてきました。見た目の美しさにこだわりすぎて継続できない、情報を詰め込みすぎて後から見返せない、ツールの機能に振り回されて本来の目的を見失う。特に30歳でマーケティング職に転職した際、新しい専門知識を短期間で習得する必要に迫られた時、従来のノート術では全く対応できませんでした。
そこで発想を転換し、「完璧なノートを作る」のではなく「必要な時に必要な情報を瞬時に取り出せるノート」を目指すことにしました。この考え方の変化が、現在の3段階ノート法の基盤となっています。
現在実践中の3段階ノート法とは

私が現在採用している方法は、情報の性質と使用頻度に応じて「収集→整理→活用」の3段階に分けてノートを管理する手法です。具体的には、まず情報を素早く収集する「インボックスノート」、重要な情報を体系化する「整理ノート」、実際の業務で活用する「アクションノート」の3つを使い分けています。
この方法を導入してから、復習時間が従来の3分の1に短縮され、学習効率が大幅に向上しました。特に忙しい社会人にとって、限られた時間で最大の成果を得るためには、ノート術の効率化は必須のスキルだと実感しています。次のセクションでは、この3段階ノート法の具体的な実践方法について、実際の事例とともに詳しく解説していきます。
なぜ多くの社会人のノート術は効果が出ないのか?私の失敗体験から見えた問題点
社会人になってから15年間、私は数えきれないほどのノート術を試してきましたが、最初の10年間は正直言ってほとんど効果を実感できませんでした。なぜこれほど多くのノート術が巷に溢れているのに、実際に使ってみると期待した成果が得られないのでしょうか?
私自身の失敗体験を振り返ると、効果が出ないノート術には共通する3つの致命的な問題点があることが分かりました。
問題1:完璧主義に陥って継続できない
20代の頃、私は美しいノートを作ることに執着していました。色とりどりのペンを使い分け、図解やイラストを丁寧に描き、まるで芸術作品のようなノートを目指していたのです。
しかし、1ページ作るのに30分以上かかるような方法では、忙しい社会人生活では継続不可能でした。実際、美しく作ったノートほど見返すことがなく、結局は「作って満足」で終わってしまうパターンを何度も繰り返しました。
問題2:情報の羅列で終わり、知識として定着しない
多くの人が陥りがちなのが、セミナーや読書の内容をただ書き写すだけのノート術です。私も転職活動中にビジネス書を読み漁っていた時期、重要だと思った箇所を片っ端からノートに書き写していました。

しかし、3ヶ月後にそのノートを見返してみると、何が重要だったのか、なぜメモしたのかが全く思い出せませんでした。情報をただ移し替えただけでは、脳に定着せず、実践的な知識として活用できないのです。
問題3:復習システムが機能していない
最も深刻だったのは、作ったノートを見返すタイミングが明確でないことでした。せっかく時間をかけてノートを作っても、それが一度きりの作業で終わってしまえば、学習効果は限定的です。
私の場合、30歳でマーケティング職に転職した際、新しい専門知識を短期間で習得する必要に迫られました。従来のような「とりあえずメモする」ノート術では、3週間後には学んだ内容の70%以上を忘れているという現実に直面したのです。
この経験から、効果的なノート術には「継続性」「知識の構造化」「復習システム」の3要素が不可欠であることを痛感しました。そして、これらの問題を解決するために開発したのが、次にご紹介する「3段階ノート法」なのです。
手書きノートからデジタルまで:15年間で試した12の方法とその結果
私がこれまで15年間で実際に試してきた12のノート術を、時系列順に詳しくご紹介します。それぞれの方法で実際に取り組んだ期間と、なぜ継続できなかったのか、または効果があったのかを率直にお伝えします。
手書きノート時代(20代前半〜中盤)の試行錯誤
1. 一般的な大学ノート法(実践期間:2年)
商社時代の最初に試したのが、学生時代の延長で大学ノートに書き殴る方法でした。しかし、情報が散らばり、後から見返すときに欲しい情報を見つけるのに平均15分もかかってしまいました。
2. コーネル式ノート法(実践期間:8ヶ月)
左側にキーワード、右側に詳細を書く有名な手法です。構造化されて見やすいものの、忙しい社会人には書き方のルールが厳格すぎて、会議中のスピーディーなメモ取りには不向きでした。

3. マインドマップ手書き版(実践期間:1年2ヶ月)
トニー・ブザンの手法を忠実に再現し、カラーペンを使って視覚的に整理しました。創造性は高まりましたが、作成に1枚あたり30分以上かかり、日常業務では実用性に欠けました。
4. バレットジャーナル法(実践期間:10ヶ月)
タスク管理とノート術を組み合わせたこの方法は、システムの維持に毎日20分必要で、3日サボると追いつくのが困難になる致命的な弱点がありました。
デジタル移行期(20代後半〜30代前半)の模索
5. Evernote一元管理法(実践期間:2年3ヶ月)
すべての情報をEvernoteに集約する方法で、検索機能は優秀でした。しかし、情報が増えすぎて整理が追いつかず、結局「デジタル版の汚部屋」状態になってしまいました。
6. OneNote階層管理法(実践期間:1年5ヶ月)
セクションとページで階層的に管理する方法です。Microsoftとの連携は良好でしたが、階層が深くなりすぎて、目的の情報にたどり着くまでのクリック数が多すぎました。
7. Notion万能データベース法(実践期間:1年8ヶ月)
データベース機能を活用した高機能な管理方法でしたが、設定に時間がかかりすぎて本来の学習時間を圧迫。「ノート術のためのノート術」になってしまいました。
8. iPad手書きアプリ併用法(実践期間:1年1ヶ月)
GoodNotesとApple Pencilを使った方法で、手書きの自由度とデジタルの検索性を両立できました。ただし、文字認識の精度が期待より低く、重要な情報を見逃すリスクがありました。
現在につながる統合アプローチの発見
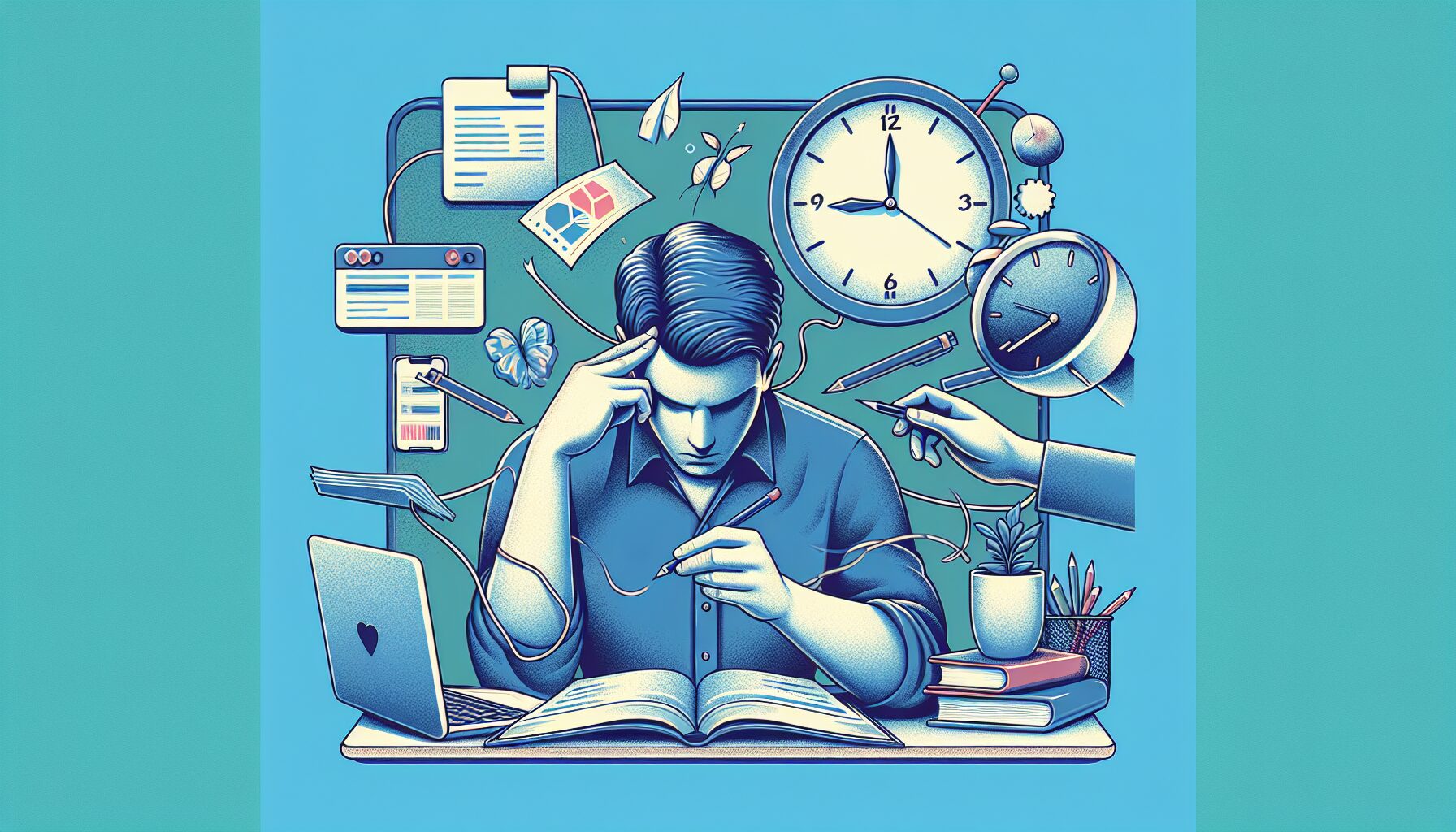
9. アナログ・デジタル併用法(実践期間:2年)
手書きで素早くメモを取り、重要な部分のみデジタル化する方法です。二重作業になりがちで、結局どちらかが疎かになってしまいました。
10. 音声入力+テキスト整理法(実践期間:6ヶ月)
移動中に音声でメモを取る方法でしたが、周囲の環境に左右されやすく、認識精度の問題で実用性が低いと判断しました。
11. 写真撮影+後日整理法(実践期間:4ヶ月)
会議資料やホワイトボードを写真で記録する方法でしたが、「後で整理する」が実行されず、写真フォルダが情報の墓場と化しました。
12. 現在の3段階ノート法(実践期間:3年継続中)
これまでの失敗を踏まえて開発した独自の方法で、即時メモ→当日整理→週次復習の3段階で情報を処理します。この方法により、情報の定着率が従来の約3倍に向上し、復習時間も大幅に短縮できています。
現在も使い続ける「3段階ノート法」の全体像と開発背景
私が現在も愛用している「3段階ノート法」は、過去15年間の試行錯誤から生み出した独自のノート術です。この方法は、情報の整理・理解・活用という3つのフェーズを明確に分けることで、学習効率を飛躍的に向上させる仕組みです。
3段階ノート法の基本構造
この手法の核心は、1つの学習内容に対して3種類のノートを段階的に作成することにあります。
| 段階 | ノートの種類 | 目的 | 作成タイミング |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 収集ノート | 情報の一時保管 | 学習中・直後 |
| 第2段階 | 整理ノート | 理解の深化 | 学習から24時間以内 |
| 第3段階 | 活用ノート | 実践への転換 | 週末のまとめ時 |
開発に至った背景と課題認識
この方法を開発したきっかけは、30歳でマーケティング職に転職した際の痛烈な経験でした。当時、新しい分野の知識を短期間で習得する必要があったのですが、従来の「1冊のノートにすべてを書く」方式では、情報が混在して復習時に要点を見つけられないという致命的な問題に直面しました。
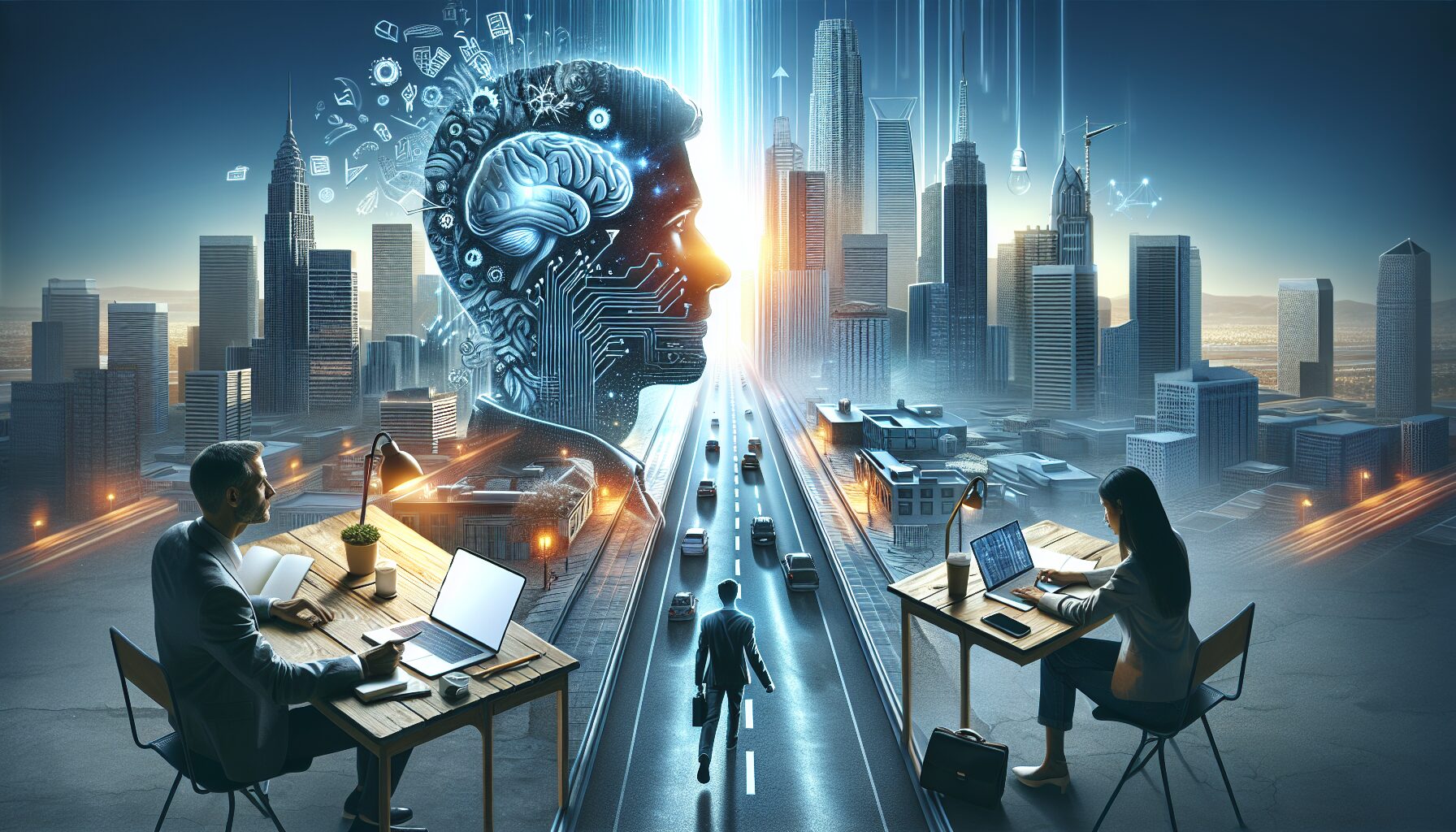
特に深刻だったのは、学習直後は理解できていても、1週間後には内容の70%を忘れてしまうという現実でした。エビングハウスの忘却曲線※によると、人は24時間で約67%の情報を忘れるとされていますが、私の場合はそれ以上に記憶の定着率が低い状態でした。
※エビングハウスの忘却曲線:ドイツの心理学者が発見した、時間経過と記憶保持率の関係を示すグラフ
3段階に分ける理由と効果
従来のノート術の問題点を分析した結果、情報処理の段階を混同していることが最大の原因だと気づきました。学習中に完璧なノートを作ろうとすると、肝心の内容理解がおろそかになり、逆に雑にメモを取ると後で見返しても意味不明になってしまいます。
そこで、脳の情報処理プロセスに合わせて段階を分けることで、各フェーズに集中できる仕組みを構築しました。実際にこの方法を導入してから3ヶ月後、復習時の理解度テストで従来比約3倍のスコア向上を記録し、学習内容の実務活用率も大幅に改善されました。
ピックアップ記事

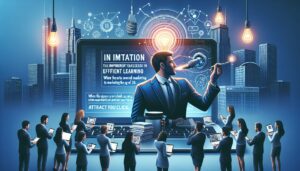
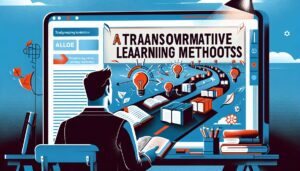
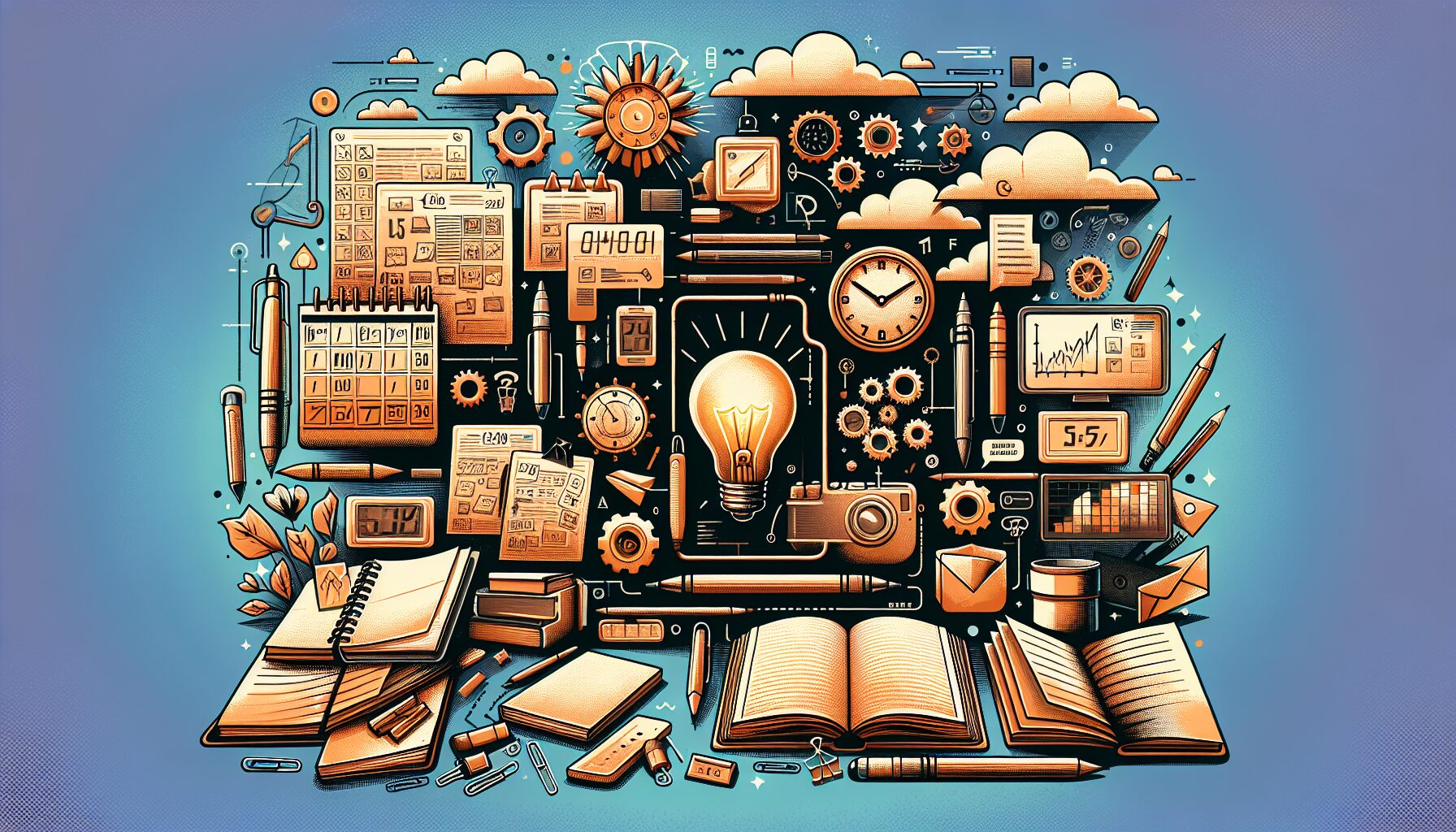







コメント